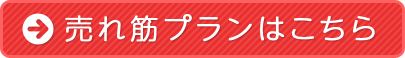- >
- >
- >
- 上越へ行こう!
上越へ行こう!
北陸新幹線上越妙高駅が開業したことで、首都圏や北陸・関西方面からも上越が近くなりました。

-
城下町高田 花ロード
10/10、11、12(3日間)
-
越後謙信SAKEまつり
10/24(土)、10/25(日)
場所:高田本町商店街
越後・謙信SAKEまつりは10周年を迎えます。
上越市と妙高市にある17の蔵元で造られる日本酒をはじめ、ワイン、どぶろく、地ビールを一同に集め、酒文化を紹介するおまつり。当日は、試飲代1,500円で清酒・ワインの試飲ができます。
また、“SAKE”に合う特産品やお土産も数多く販売されるなど、上越の食文化がまるごと味わえます。当日しか入手できない「まつり酒」の限定発売も行うほか、杜氏による伝統の酒づくり唄の披露などのイベントも多数開催します。
-
上越そばまつり
11月中旬
市内各地で栽培された新そばが一堂に集まり、地域ごとに特色あるそばの食べ比べを楽しむことができます。
お問い合わせ:025-526-5111
上越そばまつり実行委員会(上越市農政課内)
-
上越市立水族博物館
-

-
林泉寺

謙信公の祖父である長尾能景が、父・重景の菩提を弔うため明応6(1497)年に建立した寺院。ここで謙信公は名僧・天室光育の厳しい教えのもと、7〜14歳までの青年期を過ごしました。戦国の武将の中でも教養が高く、信仰心が厚い謙信公の素養はこの時期に培われたといわれています。上杉氏に替った堀氏も菩提とし、後に高田藩主も厚く保護しています。怱門(市指定文化財)は春日山城から移築したといわれ、山門は鎌倉時代の和様と唐様を取り入れた大正時代の名作です。
-
春日山神社

山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った神社です。明治34(1901)年に、童話作家・小川未明の父小川澄晴によって創建されました。日本近代郵便の父・前島密も援助したといわれています。
直線的でがっしりとした神明造の社殿は見応えがあり、境内に隣接する春日山神社記念館には、謙信公の遺品・資料などが展示されています。また、小川未明の『雲のごとく』の詩が刻まれた石碑や、童話をモチーフにした石像なども見ることができます。 -
高田公園・高田城三重櫓

高田公園は、慶長19(1614)年、松平忠輝公の居城として築かれた高田城の城跡公園です。春には日本三大夜桜、夏には東洋一といわれる蓮を楽しむことができます。
平成5年に復元された三重櫓は1・2階が展示室になっており、高田藩ゆかりの資料などが観覧でき、3階の展望室からは高田公園内が一望できます。 -
日本スキー発祥記念館

明治44年、レルヒ少佐が日本で初めてスキー技術を伝えた場所が金谷山です。記念館には当時のスキー板やスキーに関する様々な文献、レルヒ少佐の遺族から寄贈された手記など、貴重な品々が並んでいます。
-
よしかわ杜氏の郷

米どころ・酒どころで知られる吉川区は杜氏の輩出地としても知られています。ここでは、吉川の伝統文化・技術を付加して作られる地酒、乳製品の製造・販売が行われ、吉川の味・技を味わうことができます。
-
うみてらす名立

うみてらす名立は、「健康交流館ゆらら」の大浴場とプール、「海の楽市」の地場物産館、宿泊施設「光鱗」の3施設からなる、名立の一大複合施設です。目の前に迫った日本海を眺めながら楽しい時間を過ごしてください。
-
海洋フィッシングセンター

岸から日本海へと185m先へ伸びた橋の上から、安全で楽しい海釣りが楽しめます。シーズン中にはシマダイやアイナメなどが釣れます。自然の岩場を利用したサンビーチもあり、家族で楽しめる観光施設です。
※強風時、荒天時は臨時休業することがあります。 -
岩の原葡萄園

一世紀余りの時を超えて、日本のワインの歴史を物語る「岩の原葡萄園」。
日本のワイン葡萄の父と呼ばれる創設者・川上善兵衛は、この雪深い上越の地に、葡萄園を拓いてワインづくりを始めました。往事の仕事ぶりを偲ばせる石蔵の冷涼な空気は、その歳月の重みが生み出す品格と、最高級ワインづくりへの果てしない情熱を今も変わらずに伝えています。
-
上越米

上越米の粘りと美味しさは、春は山々の雪解け水が麗水となり、夏には雪解け水が自然のミネラルを含む伏流水となり田んぼを潤し、出穂後、日本海から吹く秋風により日較温度差が大きく、ゆっくり登熟することで出来上がります。
-
くびき牛

豪雪地帯であるため気温は寒く、その寒暖差から、身がしまった上質なお肉が生まれます。
広大な土地とおいしい空気の中でストレスなくのびのびと育つため、栄養価が高くうまみ成分も豊富に含まれています。 -
するてん

一夜干しの塩するめを天ぷらにしたもの。昔から上越地域で食べられている手軽な郷土料理で、お弁当のおかずや家庭料理として、またお酒のおつまみとしても絶品です。
-
ホワイト焼きそば

食による町おこしが全国で盛んになっている今、地産地消の推進および米粉の利用促進を図ることを目的とし、地域活性化の起爆剤となるための商品アイテムに「謙信公 義の塩 ホワイト焼きそば」をご当地グル メとして全国に発信中です!!
Copyright (C) i.JTB Corp. All rights reserved.